所有と経営の分離とは?そのメリット・デメリットも合わせて解説
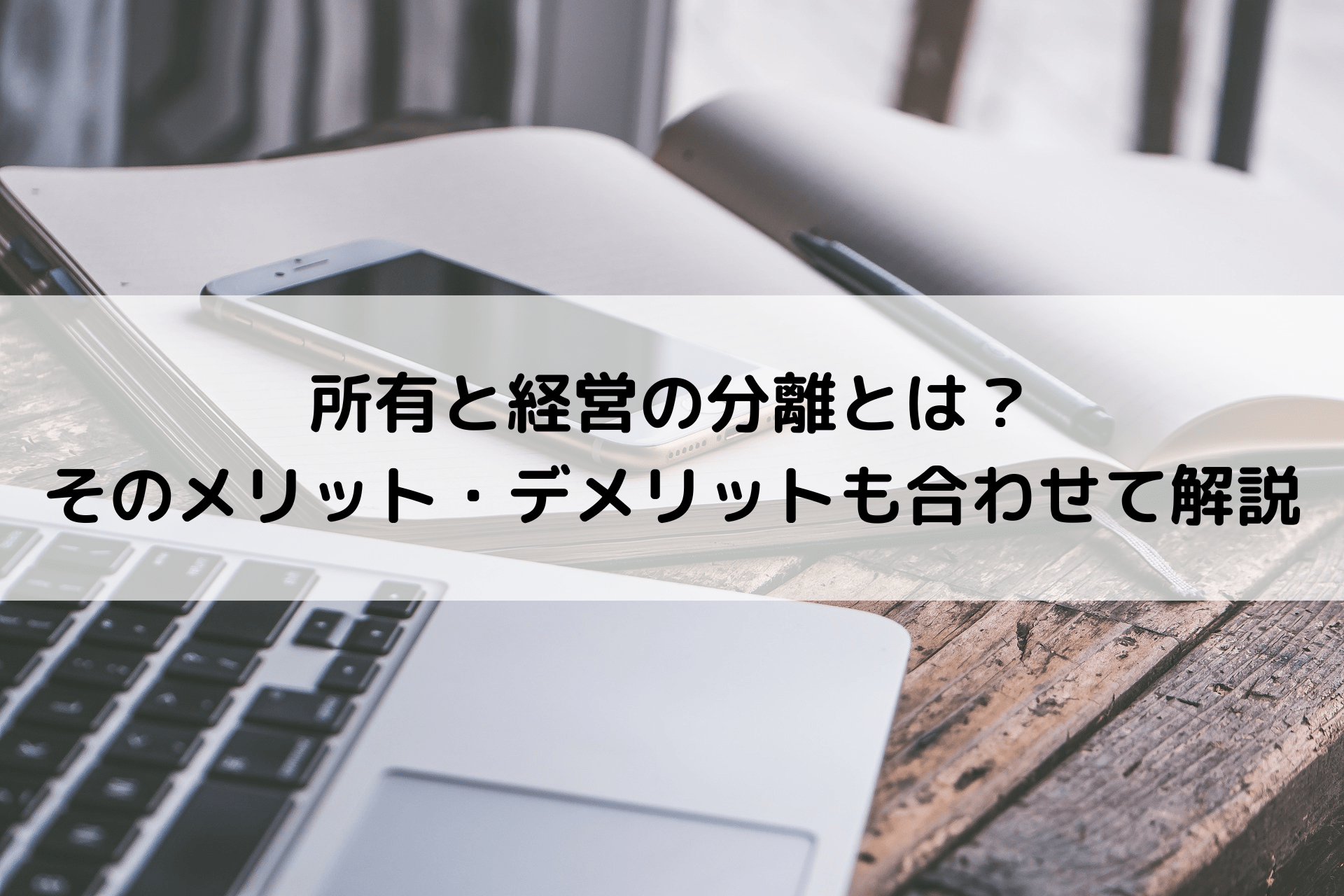
✔当記事はこのような方に向けて書かれています
「所有と経営の分離ってどういうことか知りたい」
「所有と経営の分離は何がメリットなの?」
「所有と経営の分離ってどうやるの?」
✔当記事を通じてお伝えすること
- 所有と経営の分離とは
- 所有と経営を分離するメリット・デメリット
- 所有と経営の分離をする方法
当記事では、所有と経営の分離とは何かがわかるだけでなく、所有と経営を分離する方法までご理解いただけます。
ぜひ最後までご覧ください。
所有と経営の分離とは

所有と経営の分離とは、所有者(株主)と経営者(取締役)が別人であることをいいます。
こちらでは以下2つの観点で、所有と経営の分離とは何かを見ていきます。
- なぜ所有と経営の分離が注目されているのか
- 日本の中小企業での実情はどうなっているのか
株式会社の原則
株式会社の原則は、所有者である株主と、実際に経営する取締役等の役割を明確に分担することにあります。
なぜ分担するのかというと、お金がある出資者が経営責任を負わなくて済むようになれば、より多くの人が株主となれたり、市場での株取引がより活発になるからです。
ただ原則と実情は異なります。
次章で日本の中小企業の実情をご覧ください。
日本の中小企業の実情
日本の中小企業では、株式会社の原則とは異なり、株主=経営者であることがほとんどです。
中小企業庁によれば、中小企業の72%がオーナー経営企業であることが示されています。(出典:企業の統治構造の整備状況|中小企業庁)
オーナー経営企業とは、株主と経営者が同一である企業のこと。
所有と経営の分離がなされていない中小企業が多いのです。
所有と経営を分離するメリット

こちらでは、所有と経営を分離するメリットをご紹介します。
もしメリットを感じなければ、所有と経営を分離する必要はありません。
どのようなメリットがあるかを見ていきましょう。
- 適材適所に人材を配置できる
- 資金調達がしやすくなる
- 株主の権利が保護できる:コーポレートガバナンス
- 株主へ利益の還元ができる
適材適所に人材を配置できる
適材適所に人材を配置できるのは、所有と経営を分離するメリットといえます。
なぜなら資金を持っている方がどんな事業でも経営ができるとは限らないからです。
経営を知識や経験のある方に任せて、資産家が資金提供に徹することで、自然と役割の分担がおこなわれます。
結果として、適した場所に適した人材が配置されるのです。
資金調達がしやすくなる
所有と経営を分離すると、資金調達がしやすくなります。
その理由は、株主が保有株式の割合を気にしなくて済むからです。
もし所有者と経営者が一致したままにしようとすると、株式発行で資金調達をするとその割合が崩れてしまいます。
所有と経営を分離していると、保有割合を気にすることなく資金調達ができるのです。
株主の権利が保護できる:コーポレートガバナンス
所有と経営を分離することで、コーポレートガバナンスの向上も期待できます。
なぜなら株主が、自身の利益を損なわぬよう経営を監視する体制が作れるからです。
経営を監視することで以下のような不祥事を防げるようになります。
- データの改ざん
- 粉飾決算
- 製品等の欠陥隠し
- 不正な利益提供
コーポレートガバナンスが向上すれば、金融機関などからの信頼性も上がります。
株主へ利益の還元ができる
株主への利益還元も、所有と経営を分離するメリットのひとつです。
主には以下の2つが株主の利益となります。
- インカムゲイン:配当金
- キャピタルゲイン:株式譲渡益
出資リスクに対して、利益が出たときに分配するのです。
所有と経営を分離するデメリット
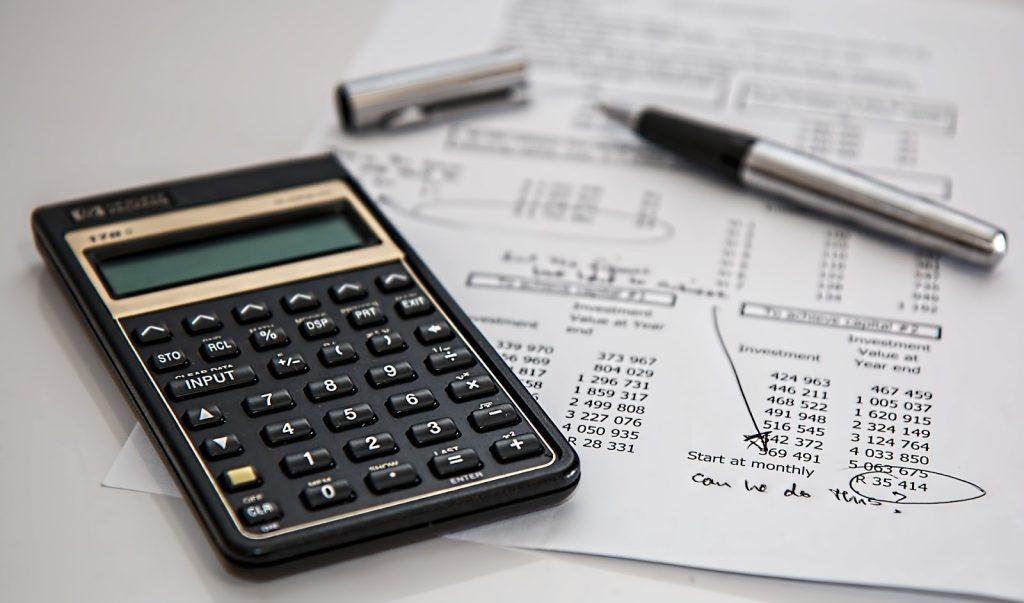
所有と経営を分離するデメリットも理解しておきましょう。
デメリットも理解したうえで、どうするかを検討すべきだからです。
- 経営方針の違い
- 意思決定に時間がかかる
- 経営者のモチベーション維持
- 株式の譲渡によるリスク
経営方針の違い
所有と経営を分離すると、株主と経営者で経営方針の違いが生まれてしまうことがあります。
利益を追求したい株主と事業を切り盛りする経営者では、置かれている立場や目指すところが違うからです。
ただし会社は所有者である株主のもの。
最終決定権は株主にあることを理解しておきましょう。
意思決定に時間がかかる
意思決定に時間がかかることも、所有と経営を分離するデメリットといえます。
なぜなら経営者は、実質雇われていることになり、全てを自分で判断できるとは限らないからです。
即決できない場面があることも覚えておきましょう。
経営者のモチベーション維持
所有と経営の分離により、経営者のモチベーションが低下してしまうリスクがあります。
その理由は、会社がどれだけ大きくなっても、役員報酬だけが経営者の受け取れる対価だからです。
対して株主は、会社が大きくなればなるほど、配当金も譲渡益も大きくなることが見込めます。
経営者のモチベーションが低下すれば、会社に大きな影響があるでしょう。
株式の譲渡によるリスク
所有と経営を分離すると、株式譲渡のリスクが高まります。
株式市場では誰でも売り買いができるのが一般的だからです。
テスラCEOのイーロン・マスク氏がTwitter社の買収を試みた際も、さまざまな意見が飛び交いました。
株主が変われば、会社の所有者も変わってしまうのは、リスクと感じる場面もあるでしょう。
所有と経営を分離する方法

所有と経営を分離する方法をお伝えします。
方法は一つではありません。
- ホールディングス化(持株会社の設立)
- IPO(株式の公開)
ホールディングス化(持株会社の設立)
持株会社を設立し、所有と経営を分離する方法があります。
持株会社は、別会社の株式を100%保有し、所有者になります。
別名ホールディングス化ともいい、たとえばソフトバンクグループ株式会社などが例です。
ソフトバンクグループ会社には以下のような子会社があります。
- ソフトバンク株式会社
- Zホールディングス株式会社
- PayPay銀行
持株会社の中にも、事業も行なう事業持株会社や、純粋に株だけをもつ純粋持株会社、金融機関の株主となる金融持ち株会社が存在します。
IPO(株式の公開)
所有と経営を分離する方法として、IPO(株式公開)も挙げられます。
IPOをすることで、株取引ができるようになるので、所有者が変わるのです。
IIPOとは、証券取引所に上場することで、誰でも株式の取引ができるようにすること。
IPOにより、所有者と経営が分断されます。
まとめ

当記事の内容をまとめます。
- 所有と経営の分離とは、株主と経営者が異なる状態のこと
- 所有と経営の分離は、株式会社の原則でもある
- 所有と経営を分離する方法は、ホールディングス化とIPOの2つ
所有と経営を分離するのは、メリット・デメリットの両面があります。
貴社にとってどちらが良いのかは、今の現状や方針により異なるのです。
まずは一度考えを整理して、今後の方針を固めていきましょう。
西山税理士事務所では、これまでさまざまな事業承継のご依頼を承って参りました。 とくに強みとしては、以下のとおり。 短期的な良し悪しではなく、長期的な視点で各経営者様のご展望に合わせた最善策を、責任持ってご提案します。 事業承継には、絶対にこれが良いという万能な解決策がありません。 できるだけ早めから、少しずつでもご準備いただくことがおすすめです。 初回のご相談は無料。いつでもご連絡お待ちしております。ご相談はお気軽に!西山税理士事務所